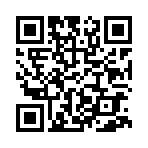2019/07/03
・
・
気楽なところで、一生懸命…と言うことです。
先日は、冷やし麺について申し上げたばかりで、
今度は「つけ麺」の噺にて、一席のお付き合いを願います。
夏でも冬でも冷やした麺を好むので、
どうやったっておしゃべりする機会が増えるって、ねぇ?
道理でございましてな。
今日は、信州松本・凌駕IDEAの「つけ麺(大盛り)」にて。
写真は「ほうれん草」のトッピングあり、です。
これまで「にごらせつけ麺」、「にぼつけ」と食べて参りまして、
シリーズのトリに「つけ麺」を選びました。
どれも麺がとても印象的なんです。
つけ麺は、やっぱり麺が美味しいからこそ輝くメニュウに思うのですが、
盛りも、ちゃんとしっかり多く、
冷たさ、締め方もキッチリされていて、
食感はツルッとした滑らかで入りの良い部分、
噛むと甘味と弾力の良さが光る…
するっと食べられるけれど、食べ応えもある太さで、
すごくすごく良いな、と。
そうして思いつくのは、
「つけ麺の3種、全部を試してみたい」と言う事です。
現在のひとつの主流である「濃厚魚介つけ麺」的なスタイルの、
「にごらせ」は旧IDEA時代からあったものですが、
より一層、美味しく感じられる様になっていたし、
「どこでも食べられるような」…「またお前か」の意で、
「またおま系」と言う言葉を昨今散見しますけれど、
名だけなら「濃厚魚介つけ麺」のカテゴリに入り、
「またおま」なのですが、
流石、凌駕と思うくらい、スープに美味しさと個性があって、
今も食べたくなるくらい。良いものでした。
「にぼつけ」は、ニボガッツの派生を感じられるもの。
美味しいですし、「にごらせ」とは全く違う…
まろやか溢れる旨味の「にごらせ」に、
尖った、インパクトある「にぼつけ」と言った印象でしょうか。
出来たら、ニンニクを入れて食べてみたい…とは、
前回のブログ化の際に書き添えた感想。
“ふつうの”と言うと、
日本ではネガティブな意味を持ちやすいので、
(絶望先生で言っておりましたし)
あまり使ってはいけないかも知れませんが、
“ふつうの”感が出ている見た目。
葱が浮く、醤油系のスープ。
甘酸っぱくて、少し辛味が入っていて、
大勝軒や、丸長に見られる様な、オールドスタイルの味付け。
これが何とも言えずに美味しいと感じました。
麺がとても生きる。
塩辛さで食べている感覚でなく、
甘味と風味と鶏でしょうか、動物感、旨味にも秀でていて。
想像通りのテイストで、想像以上に美味しかったんです。
やっぱり麺が美味しいって喜びも多いですけれど、
1杯のバランスと言うか、妙味と称えるか…
一撃必殺、インパクト勝負とも感じるラーメンとの出会いの中で、
主張があるのに、落ち着く味わいが、すごく素敵だなぁ、と。
「この記事の内容を書こう!」と決めた日の夜、
思わず、甘酸っぱい炒め物を作ってしまった。
春雨と夏野菜を和風ダシで炊いて甘酸っぱくして。
“昔懐かしい”とか、そう言うことは言わない。
でも、何だか恋しくなる味わいと言うのかなぁ…
家で、つけ麺を作るんだったら、
濃厚な魚介豚骨系でなくて、僕はこう言う1杯を作りたいのかな、
そうなのかも…と自問自答する。
自炊するなら、こう言う美味しさが良いのかも知れない。
・
・
家で作るならば、自分で食べるならば、毎日とは言わず、
でも習慣化するのならば、こうした味が僕はお気に入りだー…
…と言う意味でして。
「自炊レベルの味」とか、そう言う意味ではないです。
真似して何度か甘酸っぱいつけ麺はトライしているし、
わりと上手に再現は出来るのだけれど、
麺の旨さや味あっての調整が、やっぱり専門店は上手で。
「試してみたいなー、この味!」とも思って、こんなタイトルになりました。